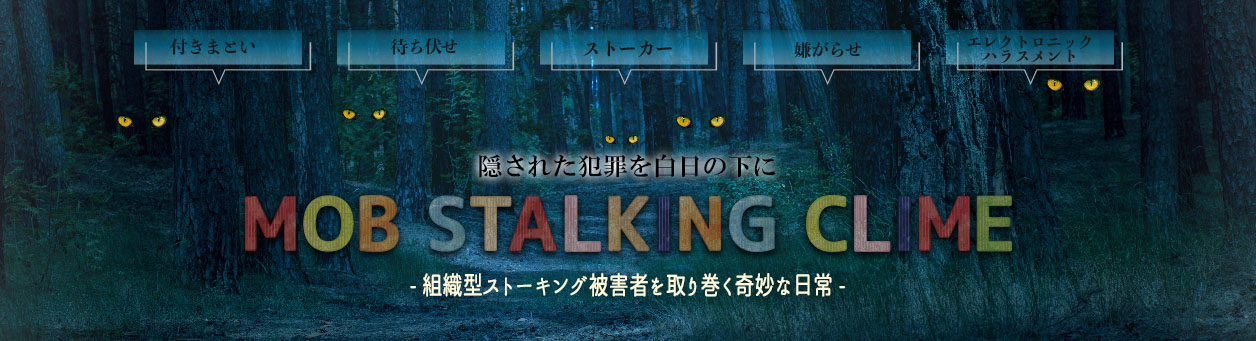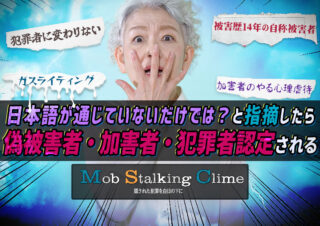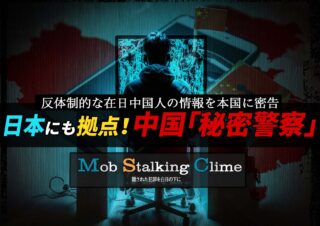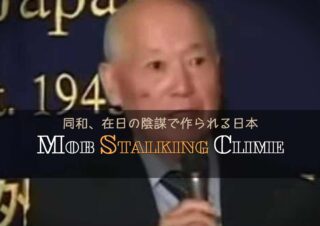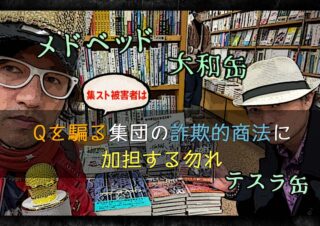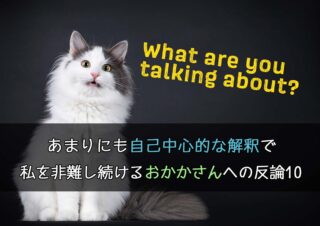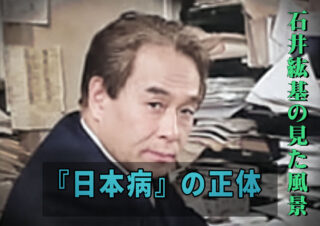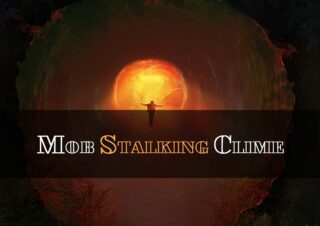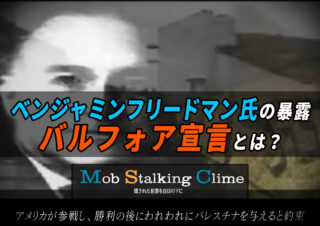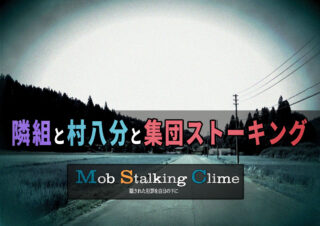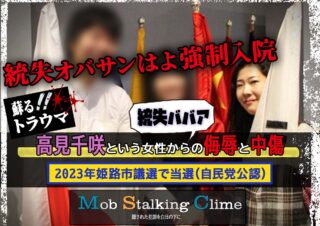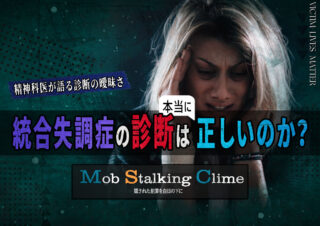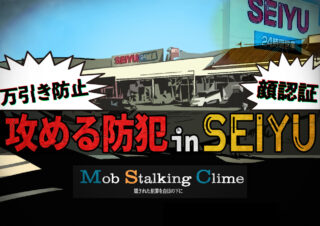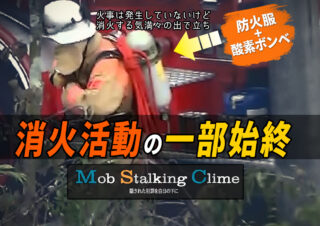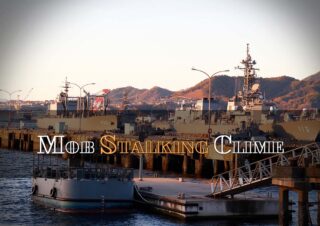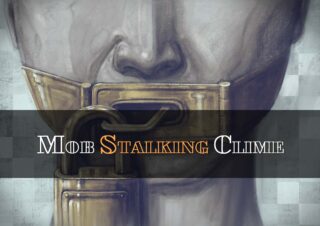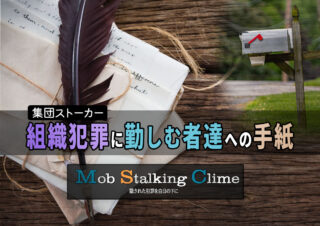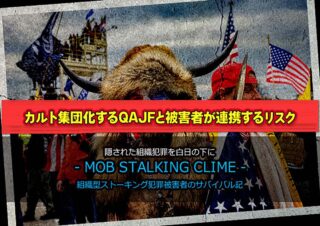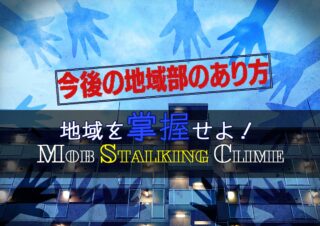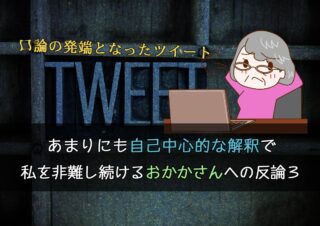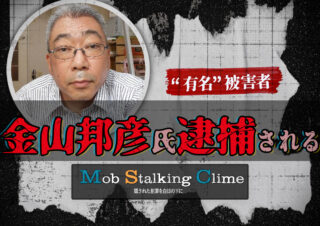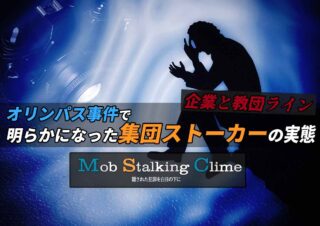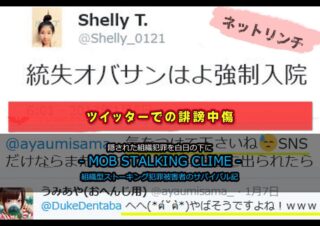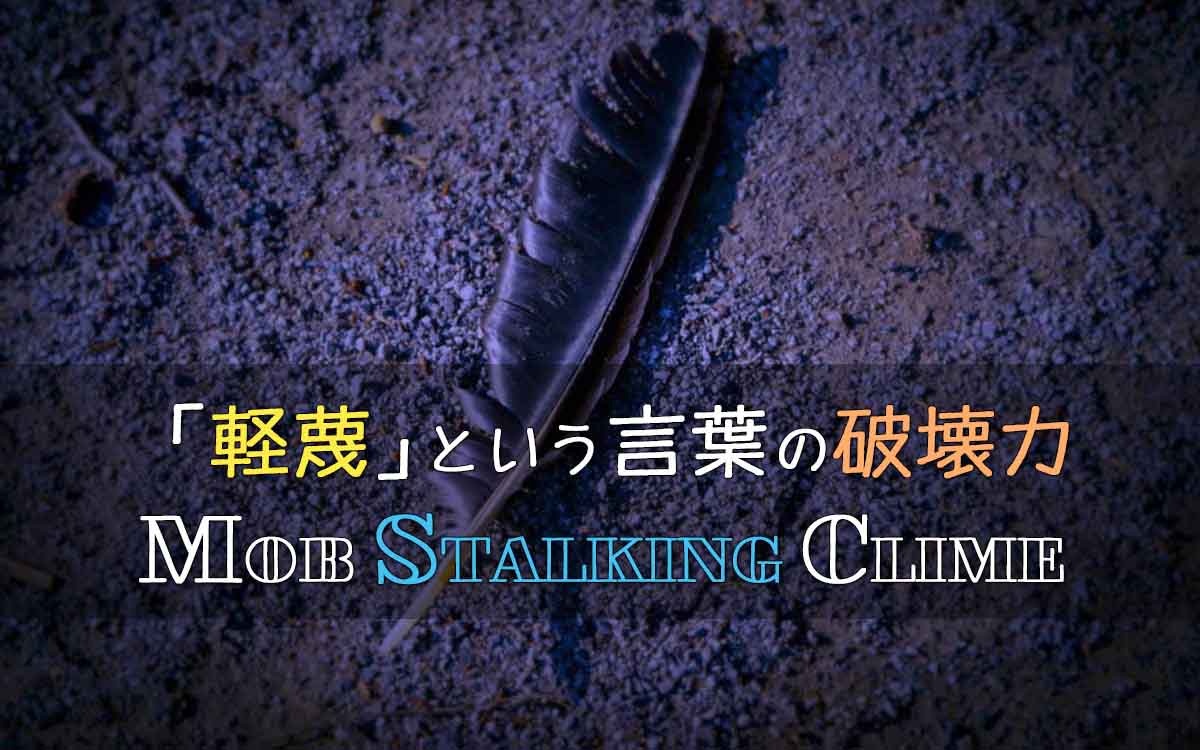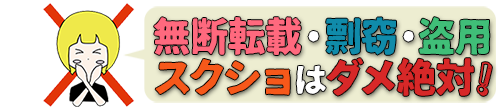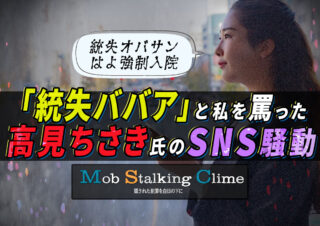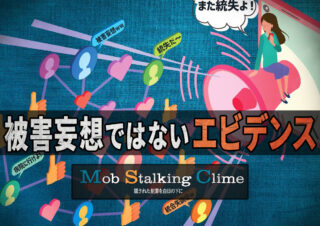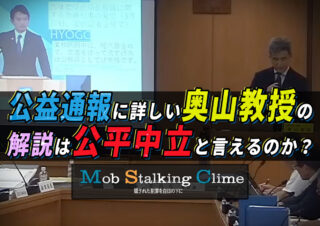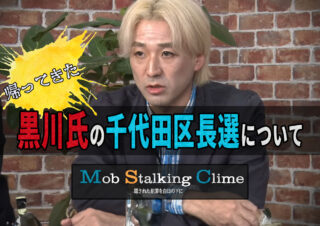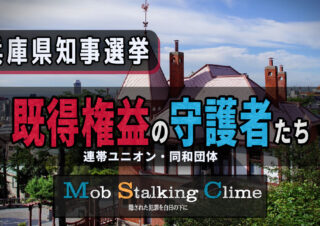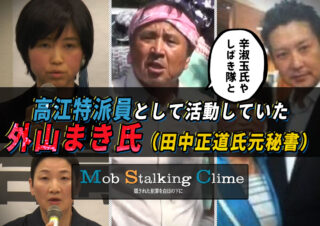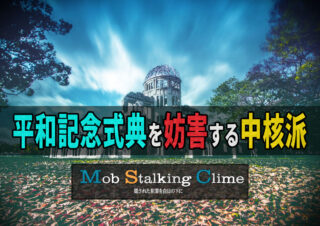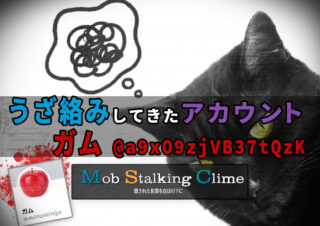年が明けて1月2日のことですが、ある方の書かれた多数の記事に対する感想をお伝えしました。その感想には私の率直な考え(本心)も敢えて含めたのですが、私の言葉足らずが原因で、最終的にその方から、「私のような発言をする人間を軽蔑する」と言われてしまいました。
またこのブログには所謂「トンデモ陰謀論」と唾棄され、嘲笑されるような内容も含まれます。そのような内容が馬鹿馬鹿しいと思う方は、今すぐこのブログから離脱することをお勧めします。どうかあなたの大切な時間を無駄にしないでください。
SNSでのコミュニケーションの難しさ

ツイッター(SNS)でのやりとりを発端としたトラブルや関係の破綻、決裂というのは、これまでに何度も経験してきましたが、改めて、限られた文字数内でのやり取りの難しさというものを噛みしめています。
特にツイッターは140文字という制限があり、一つのツイートで収まりきらない場合はスレッド形式で繋げていくのですが、私の場合、できるだけ一つひとつのツイートは、文章の途中では無く、句点(。)の場所で区切るようにしています。そのため、スレッドが長くなってしまうばかりでなく、引用したいものが次のツイートになってしまったりすることもあり、意味がわかりにくくなったり、誤解を招くことも少なくありません。
本来、気軽に交流したり意見交換するためのツールなのに、なぜか意思疎通がうまくいかなかったり、その手軽さゆえに、お互いの気持ちや状況を整理することなく剥き出しの感情そのままに相手に返してしまったりして、人間関係が決定的に破綻してしまうのは、圧倒的にSNSが多いように思います。
ブログは元々コメント欄を解放していないので、自分の言いたい事を書いて終わるため、トラブルになりようがないのですが、それでもどこかで、私の書いたブログ記事を悪用したり誹謗中傷している人物はいると思います。正当性のある批判なら別に構わないのですが、私の言っていないことまで私が言ったかのように捏造して批判するのはフェアではありません。
いずれにしても、一度自分が書いてしまったものを相手がどう受け止めるかというのは相手次第で、自分ではコントロールできないことに、今更ながら怖さというものを感じています。
本当はそのようなことは言っていないのだけれど、その部分だけを切り取られ、曲解され、断罪される、ということは少なくないと思います。そのようなシーンはSNSでは頻繁に目にするのではないでしょうか。また、私自身もそのようなことを無意識にしているのかも知れません。
その都度「補足説明」を必要とする内容はSNSには不向き

全てを十把一絡げにしているわけではなくても、「~人は」などと発言するケースは多々あります。
例えば「韓国」について話題にするケースを例にあげてみます。韓国のネットユーザーの「日本(人)を侮辱するコメント」を紹介したツイートが投稿されると、「やっぱり韓国人とは付き合えない」「断交するしかない」「だから韓国人は」というリプが沢山付きます。私も賛同する内容であれば、元の投稿をRTすることも少なくありません。
だからと言ってその人たちは、全ての韓国人を一緒くたにしてそのようなことを言っているのでしょうか?
おそらく違うと思います。私も「韓国人=全て嫌い」ではありません。韓国人の中にもいい人はいますし、好きな人もいます。例えば韓国出身の崔碩栄さんやWWUKさんがそうです。
なので韓国人だからといって全てを拒絶しているわけでもなければ、「韓国=害悪」と思っているわけでもないのですが、そのことを都度「補足説明」している人がどれだけいるのでしょうか?
そこには「言わなくてもわかるだろう」という暗黙の了解があり、そのような暗黙の了解の上に成り立っているものだと私は認識していましたし、現実的に考えて、毎回毎回補足説明を書くのは無理というか、それではスムーズなコミュニケーションが図れません。自分の思っていることを気軽につぶやくというツイッター本来の性質にも合致しない、冗長で堅苦しいものになってしまいます。
私の今回のツイートでも、「ユダヤ人」を一括りにしてなどいないのですが、「補足説明」を省略してしまったために、相手の方の逆鱗に触れてしまい、「軽蔑する」という言葉まで投げつけられる結果となってしまいました。
けれど私は、このブログでも最初から私が言及する「ユダヤ人」の定義を明確にしています。
それでも、デリケートな内容に関しては都度説明する必要があったのかも知れません。私の言葉足らずゆえ、この様な結果となってしまったことは反省すべきなのですが、言葉によるコミュニケーションというのは本当に難しいものだと、改めて思い知りました。
この人ならわかってくれるだろうとか、言わなくても大丈夫だろうとか、そういう甘えが私の中にあったのだと思います。また、あまり細かく説明すると長くなってしまうので、省略してしまったことも裏目に出てしまいました。既にその時点で相当長い文章(連続リプライ)になっていたので、できるだけ要約しなければという気持ちが強かったのです。
その方がユダヤ人に対して並々ならぬ敬意を持っていることもわかっていたのに、迂闊にも私は「ユダヤ人」とダイレクトに書いてしまったのです。
これまでの主張との整合性を保つための言及が仇に

ではなぜ私が敢えてそのような、相手の怒りを買うかもしれないリスクを冒してまでそのことに言及したのか、ということを書いておきたいと思います。
本来なら「ガス室」の矛盾についての感想だけに留めておけば良かったのですが、その記事の後半で、「ドイツはソ連の民間人を大量虐殺した」「ナチス=悪そのもの」といった記述があり、それに対しては同意することができなかったのです。
なぜなら、それについても同意してしまえば、私がこれまでにブログやツイッターで書いてきたことと180度矛盾してしまい、それでは私の今までの発言は嘘だったのか、ということになってしまいます。また私自身が納得できないのに、形だけでも同意したかのように振る舞うことも私にはできなかったのです。
ですので敢えてそのことを明確にした上で、しっかりと読んだ上での感想としてお伝えしたかったのです。多数の記事のURLを送っていただいたのに、読んだふりをして適当に感想を伝えて終わる、ということにはしたくなかったのです。それではあまりに失礼に当たると思ったから。
でも全てが私の空回りだったようです。もちろん、私の伝え方に問題があったのですが、私の思っていることをこと細かく書いていては、読む側にも負担が掛かります。それこそブログ記事を1本書くくらいのボリュームになってしまいますから、省略できるところは省略しようという気持ちの現れでもあったのです。けれどそれが裏目に出てしまったことが、今更ながらに悔やまれます。
できるだけ簡略化して伝えるべきことを伝えるというのは本当に難しいものです。文章力が問われる場面ですが、私の中にどこか油断があったことは否めません。ブログ記事の公開作業も早く進めたいという焦りもありました。
繰り返しの弁解になってしまいますが、先の韓国人の事例同様、私はユダヤ人だからといって「全てのユダヤ人が悪だ」「ヴォルシェビキと同じだ」などと思ったことは一度もありません。
以前からデヴィッドコール氏の動画なども紹介していますが、彼はユダヤ人です。ユダヤ人でありながら、アウシュヴィッツに赴いてガイドの女性に「この天井の穴はオリジナルか」と問いただし、遂にガイド長から「オリジナルではない」という言葉を引き出しています。
彼の功績は語っても語り尽くせないほど大きなものです。
他の動画は以下記事に埋め込んであります。
そして私は彼(コール氏)に対してとても好感を抱いています。決して嫌いとか憎んでいるなどということはありません。
もし私がユダヤ人というだけで、全ての人を嫌い、憎み、「ボルシェヴィキのユダヤ人」と同じであると思っているなら、コール氏の動画を紹介などしないはずです。
けれどその様な認識というのは、「言わなくても伝わっているだろう」、「前に説明しているから、都度説明する必要もない」などという甘えの上では成立し得ないものであることを、今回のやりとりを通して思い知った次第です。
それでも尚、この問題を「単なる陰謀論」とすることは、私には出来ません。
そしてまた、ドイツ兵として戦ったユダヤ人がいるからと言って、狂信的な共産主義者たちが世界に禍をもたらし、戦争を渇望し、数え切れない人間を殺害してきた罪が消えるわけでもありません。
このチェーカーなる秘密警察機構(3/4がユダヤ人)が後のシュタージへと形を変え、そして“やましい監視行為”を行っているのですが、日本にもその手先となって暗躍する者達がいるのです。そしてそれに苦しめられているのが、私たちのようなTI(Targeted Individual)と呼ばれる人たちなのです。
1917年ロシア共産党は、反革命・サボタージュ取り締まり、全ロシア非常委員会、通称チェーカーとう組織を設立しました。チェーカーは共産党が支配体制を築くために人々を恐怖に陥れ、敵を処刑する手段として利用しました。後によく知られたKGBへと発展しました。シュタージの役人達はチェーカーを崇拝し、自らをチェキストと称し、ご覧の通り記章もそっくりでした。
念を押しますが、これらの侵略行為や残虐行為、あるいは狡猾に世間を欺き人々を苦しめ、世界支配を企むユダヤ人と、何らそれらとは無縁の「平和的ユダヤ人」を一緒にしているわけではありませんので、どうかそれはご理解いただきたいと思います。
数々の史実が、キリスト教とユダヤ教との絶え間ない精神戦争を物語っている。時代を超えて常に各地で実施されたユダヤ人国外追放政策はまさにそのひとつである。フランス王フィリップ二世(1180-1223)は“ユダヤ人の悪意を見るに見かね、1182年に国土から追放した。その際ユダヤ人は家具を除く全財産を没収され、奉公人は担保として取り上げられていた元の領地に返され、すべての借金は五分の一に減らすことで帳消しにされた。”(ロジェ・グジュノ=デ=ムソー『ユダヤ人、ユダヤ主義とキリスト教徒のユダヤ化』1869年)
またブルターニュ公国の赤毛公ジャン一世は1240年4月20日に発したユダヤ人国外追放令のなかで次のように述べている。「ブルターニュ公国の諸司教、司祭、男爵、家臣らの請願にしたがい、わが公国の国益を入念に検討した結果、ブルターニュ公国からすべてのユダヤ人を追放し(…)ユダヤ人に対する借金をすべて帳消しにする」。
(中略)
「一国からユダヤ人を追放する政策は、この害虫を押し付けられる隣国に対して慈愛と公正に欠ける。またフリーメイソンを利用して国家を蝕む一部ユダヤ人の罪には加担していない残りのユダヤ人に対しても不公正だ。ユダヤ人が銀行家、商人、ジャーナリスト、教授、医師、薬剤師になることを禁止すれば済むはずだ。また国立銀行を所有する一部ユダヤ人銀行家の巨大な財産を没収することも不正ではないはずだ。一人の人間がかくのごとく金融手段を利用して短期間のうちに王家を凌ぐ富をなし、彼らを受入れている国を破産させるなど許しがたいことだからだ。」(シャルル・オジアス=チュレーヌ『ユダヤ問題と教会権』1893年)
(中略)
「ユダヤ人はたちまち富を貯え、国中の金と商品を占有するようになった。われわれに依存する状態とはほど遠く、あべこべにキリスト教徒の方がユダヤから枷をはめられることになった。この枷があまりにきつくなっても君主はなんの対策も施さないので、たまりかねた民衆は時には目を覆うばかりの暴力行為に頼るようになった。ユダヤ人に襲いかかり、虐殺が起こり、何千というユダヤ人が焼殺されたり溺死させられたりした。国が教会の指令に従ってユダヤ人を正直な職業につかせ、教皇イノセント三世、聖トマス・アクイナス、教皇ベネディクトゥス十四世が定義したとおりに、彼等にふさわしい社会的に下等な地位に留めていれば、ユダヤ人との平和共存は可能だったはずだ。」(シャルル・オジアス=チュレーヌ『ユダヤ問題と教会権』1893年)
(中略)
ヒューマニズム思想がキリスト教社会に浸透するにしたがって、人々は快適で贅沢な暮らしを好むようになり、それとともに拝金主義が高まり、キリスト教精神は衰えて行った。そのすべてがユダヤ人に有利に働いた。とはいえフランス革命前夜までは、キリスト教君主は総じてユダヤ権力の勃興を抑制する力であり続けていた。
例えば、1744年12月22日オーストリア女大公マリア・テレジア(後のフランス王妃マリー・アントワネットの母)は、国内に住むユダヤ人に黄色い目印を服の袖に縫いつけることを命じ、以下の勅令をプラハで発した。「さまざまな理由からは私は相続したボヘミアの王国に今後ユダヤ人を受け入れることを一切中止する決定をしました。これに従い1745年1月末日を最後にプラハ市には一人たりともユダヤ人が住んではなりません。ユダヤ人が発見された場合は国外に武力追放されます。しかし事業をまとめ、持参できない家財を整理するためプラハ以外のボヘミア国土にはさらに一ヶ月間の滞在を許可します。」(前掲書)
ヒューマニズム思想によってすっかり蝕まれたキリスト教社会の秩序を徹底破壊したのは、自由と平等の名の下にユダヤ人に市民権を与えたフランス革命だった。1814年から15年にかけて開かれたウィーン会議の場で、ドイツ外交官および民法専門の司法家ヨハン=ルードヴィヒ・キューブラーがユダヤ人の社会地位に関して行なった以下の警告は残念ながら無視された。
「ユダヤ、つまりユダヤ教を信仰するすべての者は手の付けようのない社会の害毒だが、目下ある程度抑制することができている。その彼等に完全な政治・市民権を与えることは、文字通りその癌細胞化を許すことで、彼等はすべてを破滅し尽くすまでわれわれの社会を蝕み続けるだろう。」
19世紀末カトリックに改宗したユダヤ人の孫で、後にオーストリア・ハンガリー帝国オロモウツ大司教となった神学者コーン神父は、教会法令の講義 (1891-92) で次のように教えていた。「ユダヤ人との関係に関する教会の指針に信徒がきちんと耳を傾けていれば、今日のようなユダヤ支配を許し、悲鳴をあげることなどなかっただろう。カトリック教会は常にユダヤ人に寛容な態度で接してきただけでなく、彼等を保護さえしてきた。だがその一方でキリスト教徒がユダヤ人とまったく同じ社会に生き、まったく同等の権利を分つことを認めたことはない。」(…)
「教会は誰よりも早くユダヤが社会の危険であることを察し、あらゆる政権に先駆けて彼等を常に隔離しなければならないことを理解した。そして心穏やかな福音精神にしたがって、教会は一方ではユダヤ人の生活を保護しながら、キリスト教徒の母親としてはキリスト教社会をユダヤの侵略から守ろうと務めた。ユダヤはキリスト教徒にとって常に精神的、世俗的な死をもたらす脅威だからだ。教会の警告に耳を傾けてさえいれば、キリスト教徒はユダヤに苦しめられることはなかっただろうし、残虐な罪をともなうユダヤに対する数々の報復行為も避けられただろう。教会の警告に従うことはキリスト教徒のためでもユダヤ人のためでもあったのだ。(…)
しかしキリスト教諸国家はユダヤ人を隔離するどころか、教会の警告を完全に無視して彼等を社会に受け入れただけでない、完全な市民権まで与えてしまった。その結果今日、ユダヤは国中の富を占有しただけでなく、国の統治権まで奪い、ユダヤにとっては“不純な”“割礼を受けてない”“ゴイム”に過ぎない非ユダヤ教国民の弾圧を目論んでいる。ユダヤに対抗できる力はカトリック教会以外にない。そしてカトリック教会がその力を発揮するには、すべての政権、そして各人一人一人が教会と協力しなければならない。それがコーン神父の教えだ。ユダヤ人がユダヤ人であり続ける限り、つまり世の終焉近くまで、ユダヤに対する唯一有効な対策は、なるべく彼等との軋轢を避け、できるかぎり彼等が害を及ぼすことを避けながら彼等を隔離する政策である。」 (シャルル・オジアス=チュレーヌ『ユダヤ問題と教会権』1893年)
エドアール・ドリュモンはまったく同じ結論をわずか二行で表している。 「一言でいえばフランスは、国内からユダヤを追放した1394年以来上昇の一途をたどり、再びユダヤを受け入れた1789年 [フランス革命] 以来、転落に歯止めがきかなくなった。」
1789年以来背教国となったフランスは、ヨーロッパ中にその毒をめぐらせ、さらにヨーロッパは世界覇権を通して全世界にこの毒を蔓延させてしまった。
※記事削除につきリンク切れ(転載元はPさんのブログ)・段落調整、強調は転載者
至る所に「ユダヤ人」という単語が出てきますが、こうした文章の中で事細かに「ユダヤ人の定義」が書かれていることは希です。それらの文献と同列に語るのはおこがましい限りですが、私も同様に、ユダヤに言及する度に、私の言う「ユダヤ人とは・・」などと付記することはありません。それはあまりに煩雑で書き手にも読み手にも負荷のかかるものだからです。
まったく思想信条の異なる人は別として、ある分野で同じ方向を向いている人にとっては説明不要でさえあると思っていました。また、自分とは真逆であったり、あさっての方向を向いている人に説明したところで、納得も理解も得られないことなど、今さら言うまでもないことです。そのような人に限りあるリソース(時間や労力)を割くのはリソースの無駄使いでしかなく、また私にとって重要でもなくどこの誰ともわからない人に対し、わざわざこのような説明をする義理も義務もないと思っています。
「軽蔑」という言葉の破壊力

あなたのような人を軽蔑する。
この言葉を投げつけられて傷つかない人はいるでしょうか。
もちろん、私の説明不足、言葉足らずが招いた結果であったことは事実ですが、それでも、「軽蔑する」という言葉を投げつけられた心境というのは、想像よりも遙かに厳しく辛いものでした。しかも閉じた空間ではなく、何百人、何千人もの目に触れる開かれた場で言われたわけですから、その衝撃と心の傷は段違いに深いものとなっていたようで、昨日からツイートを更新する気力さえ無くしていました。
全く知らない相手に言われたなら、あるいは、何とも思っていない相手からの言葉であったなら、ここまで傷つくことはなかったと思います。私のことを知りもしないで、勝手なことを言っている、程度の話で終わったと思います。
しかし今回の件では、少なからずその方の論理に共感し、なんと言っても日本に於ける「ナチガス室研究」の第一人者として尊敬してきた人であったために、私のダメージは自分の考えている以上に深いものだったようです。
それほどまでに「軽蔑する」という言葉の破壊力は凄まじいものだったのです。私もこれまでに、決して回数は多くなくとも、無意識にその言葉を使っていたと思いますが、その破壊力は、自分が投げかけられて初めてわかるのかも知れません。それでも、多くの人の目に触れる場で「軽蔑する」と言われた気持ちがどれほどのものか、想像してみてほしいのです。

私自身はこれまでにも数々の修羅場をくぐり抜けてきたので、メンタルは弱くない方だと自負していたのですが、一気に押し寄せる無気力感、何とも言えない心の苦しさを、自分でもどう処理していいのかわからず、ただ時間が解決してくれるのを待っているような状況です。
例えどんなに自分が正しいと思っても、そのような言葉を使うことは、相手の心を破壊する行為なので、私自身はもうその言葉を使うことはないと思います。ただし、組織犯罪の加害者に対してだけは使うかも知れません。
溺れる犬に石を投げる行為

こうして定期的に打ちのめされ、禍をもたらすツイッターですが、私がダメージを受ける投稿に、すかさずいいねをしたり、RTするアカウントがあります。
日頃から私に対して良くない感情を持っているのかわかりませんが、普段、ホロコーストやガス室に関してあまり興味や関心を持っているとは思えないアカウントがなぜ?と思います。私が打ちのめされる投稿を見て「ざまあ」と思ったのかも知れません。
そのようなアカウントはブロックするのが私なりの流儀ですので、見たこともないアカウントでしたが、今回もブロックしました。
自分から直接本人に突撃する勇気もないのに、他者のツイートに便乗して、安全な場所から間接的に「私への軽蔑」に賛同するような卑怯な人間とは関わりたくありません。とは言え、これは自分でもやってしまっている気がしますので、人のことは言えないのかも知れませんが、例えるなら、溺れている犬を棒で叩くような行為です。
※このことわざには「池に落ちた犬を叩け」、「水に落ちた犬を打つ」など、様々な言い方があり、どれが正しいのかわかりません。
いずれにしても、言葉は諸刃の剣。自分の思いを他者に伝えるための手段であると同時に、他者の心を傷つけ、時に殺してしまうほどの威力をもった凶器にもなり得ます。私もこれを機に、自分自身の言葉遣いを見直そうと思います。(私も今まで感情にまかせて暴言を吐いてきましたから、そんな言葉は使っていないなどと開き直るようなことはしたくありません。)
ただし組織犯罪の加害者に対しては何ら遠慮する必要はないと思っています。彼らのしている行為は、被害者の心と体を殺す行為に他ならないのですから。
言葉の暴力による精神的なダメージ
共感した記事がありましたので、いくつか引用いたします。
※もし引用がご迷惑であれば@usausaland宛てにてお知らせください。
4. うつ症状
精神的にダメージを与える心理的暴力には以下のように多くの形があります。
脅迫
コントロール不可能な嫉妬
自由の制限
プライベートの侵害
支配と服従の関係
侮辱的な言葉や呼び名
同意のない性関係
怒鳴り声、過小評価、軽蔑
金銭、服装、人間関係のコントロール
こういった暴力を受けて、被害者はうつ病の症状を見せるようになることがあります。この状態が長期間続くと自尊心が大きく傷つき、深刻な精神的被害を引き起こすことになります。
さらには、体に傷がなくとも、あまりにひどい落ち込みを経験して、唯一の解決法として自殺を考えてしまうほどになることすらあります。
軽蔑は、相手の価値を認めずに、心理的な損害を引き起こすため、最も害のある感情のひとつです。軽蔑は、思いやりと共感力がまるで感じられません。他人に痛みを生み出して、苦悩と恐怖を引き起こします。究極的には、軽蔑は感情的な人間関係まで破壊して、恐怖と低い自尊心と共に成長する子どもを作り出してしまいます。
つまり、軽蔑とは、相手のことを知るほど生まれてくる感情であることが分かります。
そして、自分と「同じだ」という類似度がなくなることでも軽蔑が生じます。
軽蔑のメカニズムとして、「相手のことを知るようになり、自分と同じという感覚がなくなり、嫌いになる」ということが仮説として浮かび上がります。
上の記事を読んでなるほどと思いました。「相手に関する情報が増えるほど、相手と自分の違いが見えてくる→自分と似ていない部分が増える→相手が嫌いになる→軽蔑する」というメカニズムが働く、というのがとても興味深く参考になりました。
そもそも自分との類似点がなく共感も見いだせない相手には最初から関心がなく、交流もしないので、好きになることも嫌いになることもないどころか、相手の存在自体知らないまま生涯を終える場合が大半ではないでしょうか。
どこか共感する(考えが似ている)ところがあるからこそ、興味や好意を持つのですが、相手を知れば知るほど、最初に抱いた好印象とは裏腹に、自分との違いが鮮明になってくるため、失望して嫌いになる、ということなのでしょう。だから距離の近い人ほどトラブルになる理由がやっとわかりました。適度な距離感が必要な理由も。

心理学で「ヤマアラシのジレンマ」という概念があります。
寒さの中、2匹のヤマアラシがいます。離れていると寒いので、体を暖め合うために体を寄せ合おうとします。しかし、近づきすぎるとお互いの「針」が相手に刺さって、痛みを感じます。2匹は近づいたり離れたりを繰り返しながら、お互いに傷つかず、ちょうどよい距離を見つけます。
このたとえは、心理的な距離が近すぎると傷つけ合うことになり、適度な距離感が重要だということを教えてくれます。
SNSに依存しすぎるのは結局不幸になるだけ。こうしたトラブルに疲れてこれまで何度もツイッターをやめようと思ったことがあります。
確かに情報収集や共有、拡散には重宝しますが、感情を剥き出しにして傷つけ合う場面も多く、トラブルに巻き込まれては時間を浪費することも多いのも事実です。やはり何かを本気で主張したい時は、手軽なSNSではなく、ブログや動画で発信していくべきだと改めて思った次第です。
ブログなら、後で読み返して不適切な表現があれば修正することもできますし、その間に気持ちの整理も付きます。しっかりと補足説明をすることで誤解や切り取りによる曲解を防ぐことができ、不用意な一言で無用なトラブルを招くこともないですから。(それでも切り取りや曲解で的外れなバッシングをする人間はいなくならないでしょうけど)
人は「正しさ」というこん棒を手に入れた時に、容赦なく相手を叩くものだから。そして正しさという安全地帯にさえいれば、自分が攻撃されたり批判されることがないため、安心して相手を叩くことができてしまうのですね。
正しさのバリアによって安全に守られながら、相手を傷つけたり攻撃したりする残酷な人々の様子は、ぼくには決して正しいふるまいだとは思えない。
人間がいつでも正しい生き方ができるとは決して限らない以上、どうしようもない運命に翻弄されればされるほど、真摯に人生や自分と向き合って生きれば生きていくほどに、自らの過ちや間違いや悪と真剣に対峙せざるを得なくなる。そして次第に、この世の正しさや常識や道徳の中にある浅はかさと偽りに気づかされるのだ。
深く傷ついたとは言え、今回の件は私の不用意な発言が原因でした。ゆえに相手の方を責めるつもりで書いたものではありませんが、人の体を癒やす尊い職業に就かれていらっしゃる方が、言葉によって他者の心を壊すようなことは、どうかされませんようにと切に願うばかりです。そして人間関係というものは、かくも難しいものであり、信頼関係を築き上げるのは何年も何十年もかかるのに、壊れる時は本当に一瞬であることを、また一つ体験した2022年の年明けとなりました。
その一言が未だ心に突き刺さったままではありますが、この記事を書いて区切りとします。